
マーケティングWeekとは、年に3回開催される日本最大級のマーケティング総合展示会です。2025年6月18日(水)から20日(金)の3日程で東京ビックサイトで開催され、3日間で17,537名が来場しました。展示会全体は『販促 EXPO』『Web・SNS活用 EXPO』『データインサイト EXPO』『広告メディア EXPO』『クリエイティブTech EXPO』『営業支援 EXPO』『ECグロース EXPO』『CX・顧客育成 EXPO』『マーケター採用・育成支援 EXPO』の9つで構成されています。
今回デジぽち編集部は報道関係者として、特別講演のほか『Web・SNS活用 EXPO』『CX・顧客育成 EXPO』を中心に各社のブースを訪問しました。
本記事では、展示会を通して見えてきたマーケティングトレンドをご紹介します。
生成AI時代のマーケティング最適化戦略

▲「AI」「Chat GPT」キーワードのブースが多数
SEOと生成AIの関係性「AIオーバービュー」
今回の展示会では多くのブースで「AI」「パーソナライズ」などのキーワードが目立ちました。まず着目したのは、SEO(検索エンジン最適化)と生成AIとの関連です。特に、疾患啓発サイトやオウンドメディアを通じてユーザーとの接触を図るうえで、生成AIの活用に関心を寄せるメディア運営者の方も多いのではないでしょうか。
従来、検索行動といえば、GoogleやYahoo!といった検索サービスを活用するのが主流であったことは言うまでもありません。しかし、生成AIの登場により、この検索行動は大きく変化しつつあります。
なかでも代表的なのが、生成AIによる要約表示(SGE:生成AIによる検索体験 や LLMO:大規模言語モデル最適化)です。たとえば「まずは質問する」場面を想定してみましょう。従来は、検索エンジンがユーザーの入力に対してマッチしたページのリンク一覧を返す、というものでした。しかし生成AIでは、「ダイレクトな回答」や「関連情報の提示」、あるいは「追加の質問を返す」といった双方向性のある応答が可能になり、ユーザー体験がその場で完結するケースも増えています。
こうした変化を受け、SEOの役割も変わりつつあります。これまでのように「検索結果で上位に表示されること」が重要だった時代から、「生成AIに引用されるような構成・情報設計を行うこと」が重視される時代へと、軸が移行しているのです。
では、実際にメディア運営者はどのように対応すればよいのでしょうか?出展企業の説明によると、具体的な行動として「見出し完結型の構成」や「Q&A形式の記事設計」など信頼性の高い引用元として認識されるための工夫を施すことで生成AI時代に対応できるケースもあるようです。
とはいえ、AIトレンドは数か月単位で急激に変化する領域でもあります。継続的に最新情報をキャッチアップしながら柔軟に運用方法を見直していく。遠回りに見えても、それが最終的には堅実な運用につながるはずです。
AIによる業務自動化
ブース訪問では、AI活用における新たな潮流として「マルチエージェント構造」への移行もひとつのポイントであると伺いました。これは、AIをひとつの業務に閉じ込めるのではなく、複数のAIエージェントがそれぞれの役割を分担し、連携しながら業務を処理していくという構造です。
例えば、「FAQ対応」→「要件抽出」→「資料作成」→「スケジュール提案」といった一連の業務を、各エージェントが”バトンリレー”形式で担うことで、より効率的な業務遂行が可能になります。
さらに、NCP(ノーコード・コネクト・プロトコル)の登場により、AI同士やマーケティングツール・CRM・チャットなどのシステム間連携が、エンジニア不要で実現可能となりつつあります。これにより、非エンジニアでも業務フローの自動化や改善を柔軟に設計できる環境が整ってきています。
ユーザー視点で組み立てるコンテンツ戦略
次に注目したのは、「ユーザー視点に立ったコンテンツ設計」です。メディア運営者であれば、「どうすればユーザーの興味を惹きつけるコンテンツをつくれるのか?」は、常に関心の高いテーマのひとつではないでしょうか。
共感を軸にした顧客体験
特別講演『auが追求しつづける“共感”-生成AIを活用した顧客体験』の第1章では、広告における「共感」を主題として取り上げていました。特に、顧客の“トップ・オブ・マインド”や“純粋想起”を獲得するためには、短期記憶の積み重ねを通じて長期記憶へと定着させることが重要である、という点が強調されていました。
このプロセスにおいて「共感」は極めて重要な要素である一方で、「共感を生み出すこと自体の難しさ」についても言及されていたのが印象的でした。
また、携帯キャリアという商材は検討・乗り換えまでに時間がかかるため、長期的な視点でのブランド構築が必要であるという話もありましたが、この考え方は、ある企業が他社を通じて最終消費者に製品やサービスを提供するようなBtoBtoC型のビジネスモデルにも通じるものがあるかもしれません。
 では、「共感」はどのようにして生まれるのでしょうか?特別講演では、AIDMAやAISASといった消費者行動モデルにおける「興味・関心」のフェーズを引き合いに出しながら「どのようにインサイトを捉え、ユーザーの好奇心を喚起するか?」という視点から解説が行われましたが、下記のグラフをもとに、ある興味深い知見が紹介されていました。それは、「予想と情報の不一致(情報ギャップ)」が小さすぎても大きすぎても反応が薄くなり、ほどよい中間のギャップがもっとも好奇心を刺激するというものです。
では、「共感」はどのようにして生まれるのでしょうか?特別講演では、AIDMAやAISASといった消費者行動モデルにおける「興味・関心」のフェーズを引き合いに出しながら「どのようにインサイトを捉え、ユーザーの好奇心を喚起するか?」という視点から解説が行われましたが、下記のグラフをもとに、ある興味深い知見が紹介されていました。それは、「予想と情報の不一致(情報ギャップ)」が小さすぎても大きすぎても反応が薄くなり、ほどよい中間のギャップがもっとも好奇心を刺激するというものです。
この“ちょうどいい違和感”を生み出すことが、ユーザーの注意を引き、共感につながるファーストステップになるという考え方は、非常に示唆に富んでいます。
 もし疾患啓発サイトのコンテンツを企画するのであれば、例えば「よくある誤解」から導入する教育的な構成や、患者インサイトに基づいた問いかけ型のコンテンツなどが、ユーザーの関心を引きやすい形式として有効かもしれません。
もし疾患啓発サイトのコンテンツを企画するのであれば、例えば「よくある誤解」から導入する教育的な構成や、患者インサイトに基づいた問いかけ型のコンテンツなどが、ユーザーの関心を引きやすい形式として有効かもしれません。
ユーザー行動を軸にしたコンテンツ設計
ブース訪問では、生成AIによる記事コンテンツに対してペナルティのリスクがあるという話題もお聞きしました。実際、Googleは「AIで大量に生成されたコンテンツへの対策を強化する※1」 方針を発表しています。
こうした背景を踏まえ、単に記事を量産するのではなく、滞在時間やサイト内回遊、読後の行動といったユーザーの体験を意識した「読まれるコンテンツ」の重要性を、各社で改めて強調されていました。
医療・製薬業界でのマーケティングに活かすには
今回は、最新技術の活用から、ユーザーの共感を呼び起こすための「一歩先の気づきを与えるコンテンツ設計」の考え方まで、簡単にご紹介しました。特に生成AIの活用については、以下のような注意点が指摘されています。※2,3
•知的財産権など他者の権利侵害
•個人情報・機密データの漏洩
•誤った情報の生成(ハルシネーション)
•利用方法・目的などに関する所属企業の規定の逸脱
こうしたリスクを理解したうえで、信頼される情報をユーザー視点で継続的に発信していくことが、これからのメディア運営においてますます重要になっていくでしょう。
エムスリーデジタルコミュニケーションズは、医療・製薬業界の実行支援を徹底的にサポートします。業務上のお困りごとは、業界経験を豊富に有した弊社までご相談ください。
【参考記事】
※1 大量生成されたコンテンツの不正使用(Google)
※2 生成AIはじめの一歩~生成AIの入門的な使い方と注意点~(総務省)
※3 コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック(経済産業省)
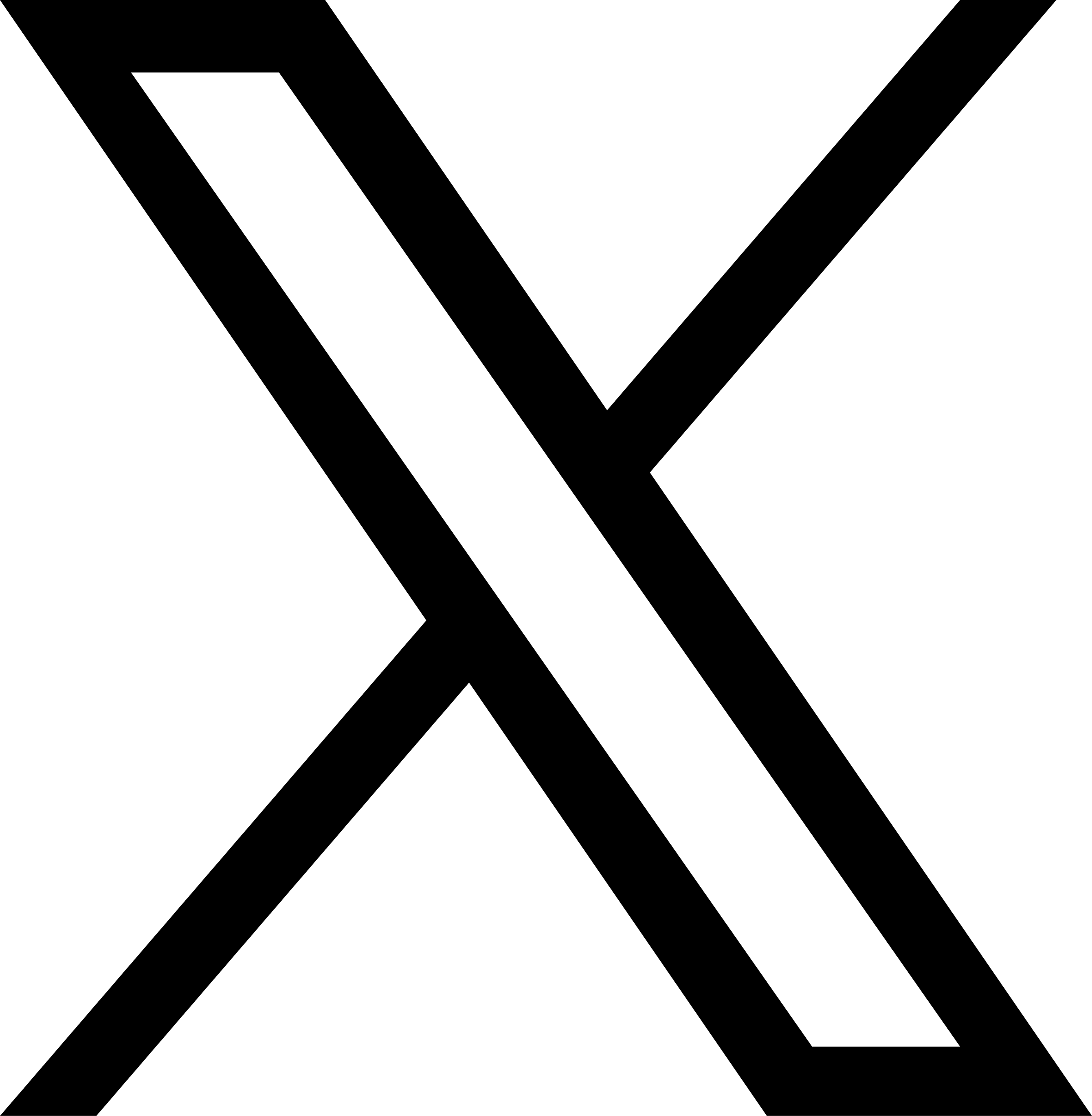





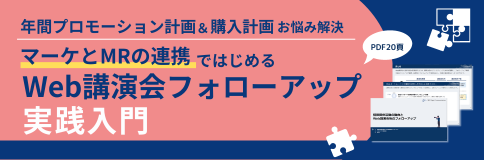

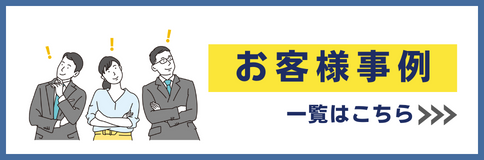
.png?width=733&height=412&name=IPC_%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3KV_%E3%83%9F%E3%82%AF%E3%82%B9(%E5%86%8D%E7%94%9F%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%E5%85%A5%E3%82%8A).png)

.png?width=733&height=412&name=SEM240805(%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AA%E3%81%97%E5%86%8D%E7%94%9F%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%E5%85%A5%E3%82%8A).png)
.png?width=733&height=412&name=PMD%20%E5%8C%BB%E7%99%82%E5%BE%93%E4%BA%8B%E8%80%85%E3%81%8B%E3%82%89%E5%AD%A6%E3%81%B6%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%96%B6%E6%A5%AD%E3%81%AE%E3%83%92%E3%83%B3%E3%83%88(%E5%86%8D%E7%94%9F%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%E5%85%A5%E3%82%8A).png)