昨今、IoT・AI・ロボット工学など医療機器への技術応用が急激に進み、世界的な高齢化などの後押しもあって医療機器業界は成長市場とみなされています。 専門機器を用いた正確な診断/治療や患者のWell-being実現には、メーカーの努力だけでなく現場を担う医療従事者との協働が欠かせません。
そのような背景の下、医療現場では正確な検査データから診断・治療に、メーカー側では適正使用の啓蒙・マーケティングに、定常的にコストをかけています。しかし両者の交流機会の少なさもあり、それら活動はお互いに伝わらないことも多いのが現状です。
今回は臨床検査の視点から、国際医療福祉大学 教授/臨床検査技師の清宮先生に医療従事者として現場で大切にしていること、医療機器メーカーに求めることについてお話いただきました。
| 本記事は2022年10月5日開催「Pharma Marketing Day 2022 presented byデジぽち」のセミナーセッションを記事にしています。内容は当時のものとなりますのでご了承ください。 ▶ 動画版のご視聴はこちら(無料) ▶ デジぽち最新の動画はこちら |
登壇者
国際医療福祉大学 成田保健医療学部 教授 清宮 正徳
エムスリーデジタルコミュニケーションズ株式会社 マーケティング 秋葉 彩乃
前回の記事はこちら>>
【トレンド】医療従事者から学ぶ 医療機器営業のヒント~患者データを扱う心構えや現場のニーズ~(1/2)
医療従事者が感じる医療機器メーカーの営業活動
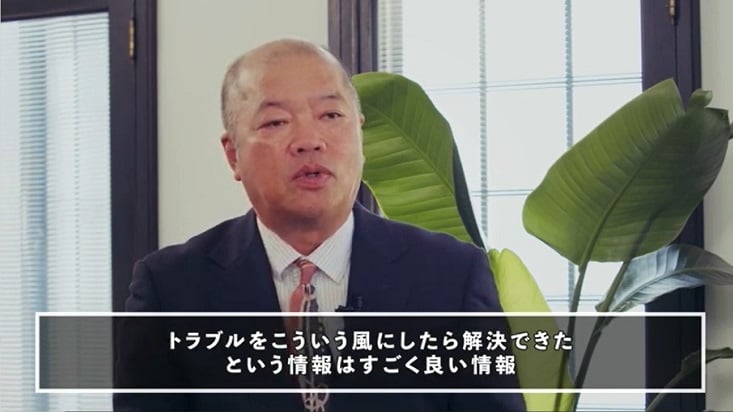
秋葉
医療従事者のお立場から見て医療機器メーカーの営業/学術営業/本社マーケティング担当の方に伝えたいことをお聞きしたいと思います。清宮先生、いかがでしょう?
清宮
そうですね、私の立場から何か申し上げるのは難しい所でもありますが、検査の話ではトラブル時にどのぐらい即座に解決できるか、あるいは現場に駆け付けられるかを現場は重視しています。非常時に迅速かつ真摯に対応することでユーザーの信頼を厚くできる可能性があると思います。ですのでトラブルは必ずしもピンチではなくチャンスと考えます。困っているユーザーと一緒の立場になって考えて頂けると良いのではないでしょうか。
トラブルをこういう風にしたら解決できたという情報はすごく良い情報のはずなのですが、メーカーさんにからすると、トラブルを公開する時点で「そんなにトラブルがあるの?」というイメージを持たれてしまうのか、なかなか表に出てこないんですよね。データベース化して希望するユーザーが閲覧出来るように公開できるとすごく良いと思いますが、現実は中々難しいのかなあ、と思っています。
秋葉
これまで、企業からは提供されてこなかった所かもしれませんね。例えば、よくあるトラブル集ですとか、 かみ砕いて提供する形もあり得ると思います。

清宮
そういうものがあればもちろんいいですね。例えば消耗部品の洗浄や交換を怠るとどういうトラブルにつながるか、などの事例なら「こうすれば防げますよ」という前提の話ですので、メーカーの不名誉にはならないと思います。
そういったアフターサービスといいますか、普段の対応が良ければ、次回の機器更新の時期にも「あのメーカーにしようか」という話にもなり得るので、そういう仕事というのは一見すると営業に直結しないように思えるのですが、長い目で見ると利益になっていくのではないかと思います。
またメーカーさんが定期的にユーザーを訪ねるのも良いと思います。稀に一方的に説明をして満足して帰ってしまう営業がいますね。営業はかえって口下手な方が向くのではないかと思うことがあって、情報を提供するのではなくて、「どのぐらいユーザーから色々な話をもらえたか」という方が重要になってくると思うのです。その方がユーザーの印象も良いのではないかと思うのです。

秋葉
視聴者のみなさんには耳が痛い話もあるかもしれませんね。「話す営業よりも聞く営業が大事」ということですが、具体的にはどのようなことをヒアリングしてほしい、あるいは話題にしてほしいと感じていらっしゃいますか?
清宮
導入している試薬や装置に対する意見では、誉め言葉をもらって喜んで帰ったのでは、営業の意味があまりないと思います。むしろ「何かお困りごとやお気づきの点はありませんか?」とこちらから水を向けてみると良いのではないでしょうか。
秋葉
そうですね。現場での話題、様々あるかと思うのですが、「今困っていることありませんか?」と聞かれて忙しい現場ですぐに回答できる医療従事者もそんなに多くないのかなと、個人的には思ったんですよね。ですから、検査室内での話題から入っていくのも良いですし、やはり「何を聞きたいか」受け手の方は「何を話したいか」の事前準備をお互いにできる段取りをしておくのが良いのかなと思いました。
デジタルと訪問のハイブリッド営業は通用するか

秋葉
ちなみに営業『訪問』だけではなく、デジタルを用いたハイブリッドな コミュニケーションのあり方というのも受け入れられると思いますか?
清宮
そうですね、可能性はあると思いますが、画面越しではうまくニュアンスが伝えられないこともあります。誰が見ているかわからない状況というのは「ここだけの話」といった話がし難いし証拠が残ってしまうのは痛いので、基本は訪問が良いと思っています。一方、試薬の検討データや、学会発表内容の確認など、メーカーの学術担当の方は忙しくて全国などいけないかと思いますので、細かな情報のコミュニケーションはデジタルのコミュニケーションを使って、「ここだけの話」といった訪問も上手く両立されると良いと思います。
秋葉
なるほど、やはり使い分けというところは今後も重要になって来るのではないかと思いました。デジタルも活用しながら、ぜひ有効な関係を作っていただければと思います。また、お話を伺いながら、これらはある程度の関係値がすでにあるからこそできることだとも感じました。
認知度の低いメーカーの製品はどうやったら使ってみたいというニーズを聞けるのか?
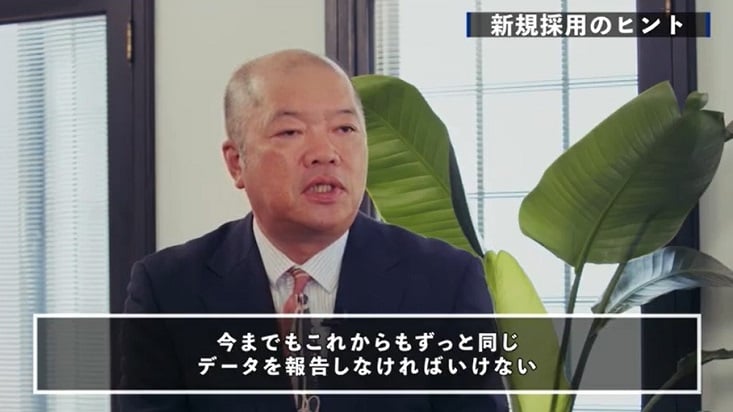
秋葉
本セッションにお申込み頂いた方から事前にこちらのご質問を頂きました。
「認知度の低いメーカーの製品はどうやったら使ってみたいというニーズを聞けるのか?」 というご質問です。
新規開拓というお話になると思うのですが、このあたりはどのようにお考えですか?
清宮
我々は今までも、これからも、ずっと同じデータを報告しなければならないので、正直にいえば新規メーカーの製品を使用するのは不安があります。失礼ですが、会社がつぶれたり事業から撤退したりしてしまうこともありますので。
そこを超えて採用してもらうには、低価格・高性能の両立が必要だと思います。
まずは学会発表や基礎研究をやってる施設にデモを依頼し、学会発表をしてもらうのが良いと思います。必ずしも大病院でお願いするのではなく、普通の病院でもよいのです。いくつか発表がありますと説得力も増してきますので、たとえ採用に至らなくても、無駄足を覚悟でデモンストレーションが必要と思います。機器や試薬の性能で最も重大なのが「データの継続性や安定性」だと思います。長期にわたって精度が維持できることを示していけると良いと思います。

秋葉
ありがとうございます。なかなか厳しいというご意見もいただいたのですけれども、データの継続性を重視するというところは、医療従事者だからこそのご意見だと思います。
清宮
ありがとうございました。
| 本記事は2022年10月5日開催「Pharma Marketing Day 2022 presented byデジぽち」のセミナーセッションを記事にしています。内容は当時のものとなりますのでご了承ください。 ▶ 動画版のご視聴はこちら(無料) ▶ デジぽち最新の動画はこちら |
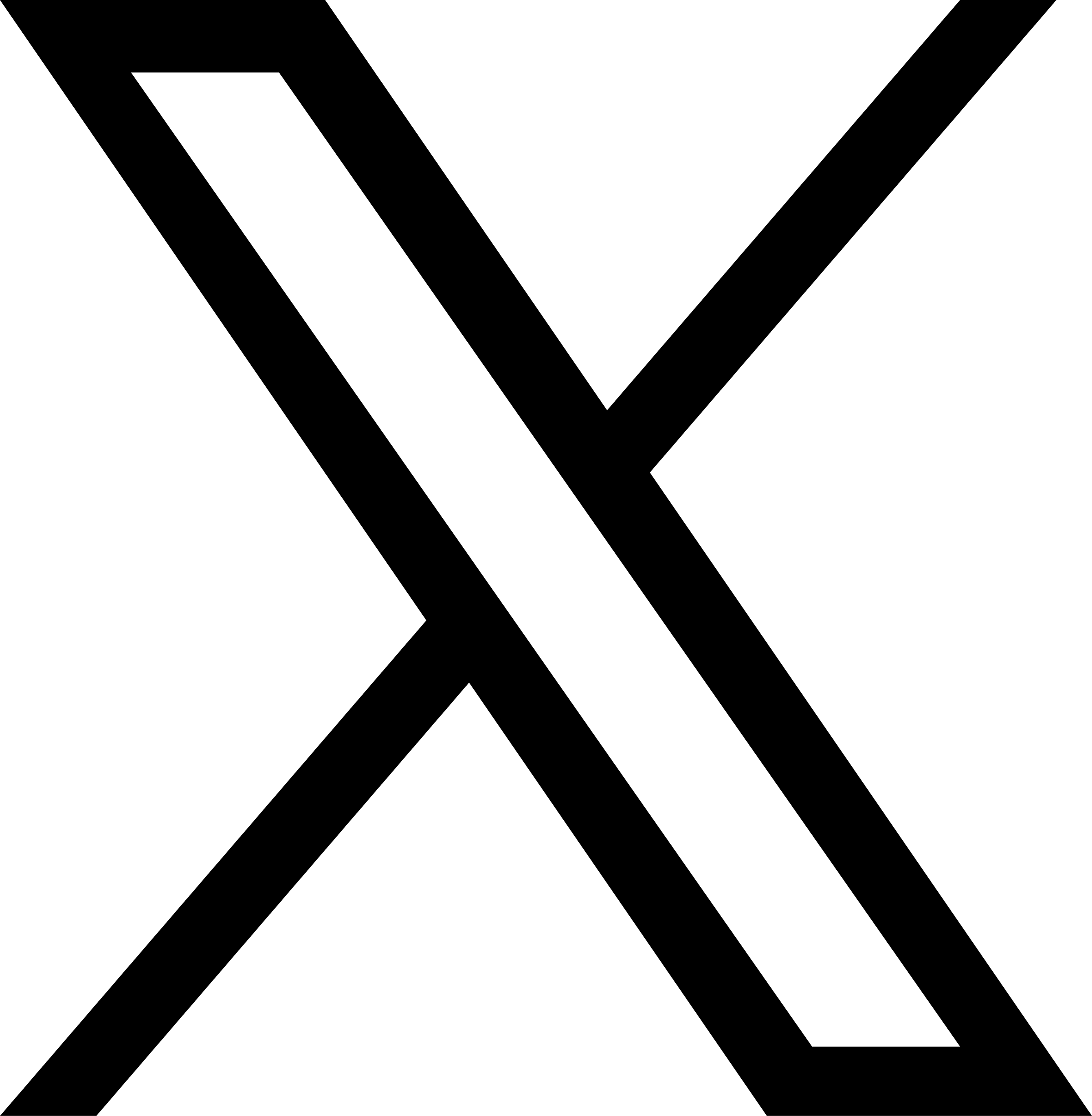





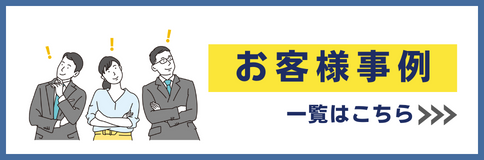


.png?width=733&height=412&name=IPC_%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3KV_%E3%83%9F%E3%82%AF%E3%82%B9(%E5%86%8D%E7%94%9F%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%E5%85%A5%E3%82%8A).png)