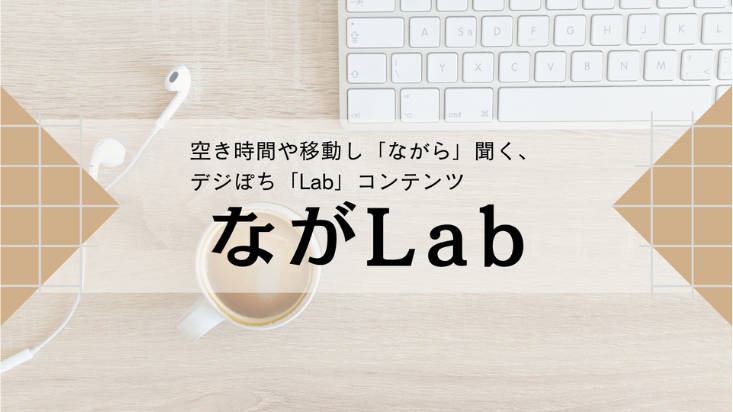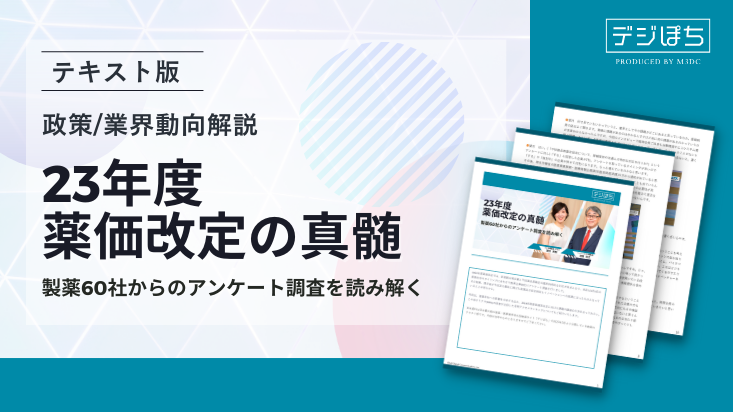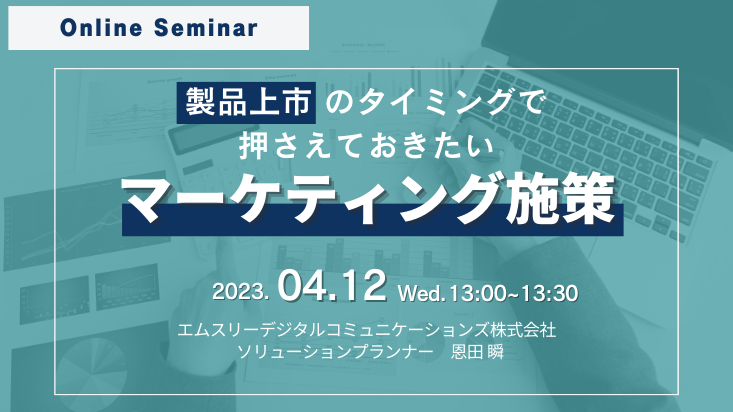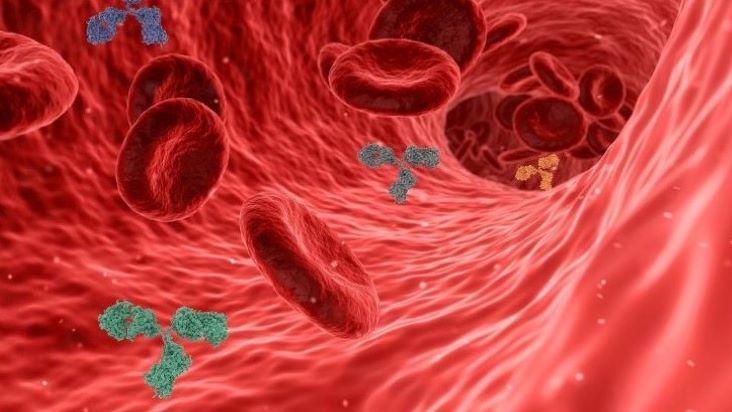画像:Freepik.com
【HowTo】購買・オムニチャネル担当者様向け 運用と支出を最適化!Web講演会運用を見直す5つの切り口
2023年6月29日 更新
「運用と支出を最適化!Web講演会運用を見直す5つの切り口」資料請求は以下のフォームより承っております。お気軽にご連絡ください。
【セミナー】臨床試験の更なる飛躍へ 動画を活用した同意取得の効率化提言 ~ガイダンスの発出を受けて~
2023年6月27日 更新
7月19日に臨床開発、治験・臨床研究・PMSのご担当者様向けの無料オンラインセミナーを開催いたします。
【セミナー】MEP x DigiProで顧客接点の統合を実現 情報提供活動の一元管理で医師CXを改善
2023年6月8日 更新
6月21日に医薬品・医療機器の営業、マーケティング、プロモーション、デジタルコンテンツ担当者様向けの無料オンラインセミナーを開催いたします。
【コラム】ながLab~空き時間や移動し「ながら」聞く、デジぽち「Lab」コンテンツ~
2023年5月19日 更新
少し空いた時間や移動中など何かと並行しながら、耳から情報を取り入れることができます。
【事例紹介】情報サイト「正しく知りたい!遺伝性乳がん卵巣がん」を公開
2023年5月9日 更新
遺伝子検査のリーディングカンパニーであるミリアド・ジェネティクス合同会社 様は、日本ではまだ認知・理解の低い「遺伝性乳がん卵巣がん(HBOC)」の疾患啓発サイトの構築/公開を検討していました。
そこで、弊社から、多くの方にHBOCや遺伝子検査に関する情報を発信するためのサイトのコンセプト、タイトル、サイトマップ、具体的なデザインなどをご提案。2023年3月に情報サイト「正しく知りたい!遺伝性乳がん卵巣がん」を公開しました。
サイト公開に合わせて、SEO対策やサイト告知/遷移を図るためのリスティング、GDN、Instagram、YouTubeなどの広告制作/配信も実施しました。
【トレンド】23年度薬価改定の真髄 製薬60社からのアンケート調査を読み解く テキスト版無料ダウンロード
2023年4月19日 更新
「23年度薬価改定の真髄 製薬60社からのアンケート調査を読み解く」の資料請求は以下のフォームより承っております。
お気軽にご連絡ください。
【セミナー】製品上市のタイミングで押さえたいマーケティング施策
2023年3月27日 更新
4月12日に、製品上市前後のマーケティング施策について押さえるべき基本的なポイントや最新のトレンドを紹介する無料セミナーを配信いたします。情報収集中のプロダクトマネージャーやマーケティング担当者様は是非ご視聴ください。
【トレンド】オンコロジー最前線#2:乳がん治療のアンメットニーズの克服に挑む抗体薬物複合体(ADC)
2023年3月24日 更新
【トレンド】オンコロジー最前線#1:進化する抗体薬物複合体(ADC)
2023年3月24日 更新
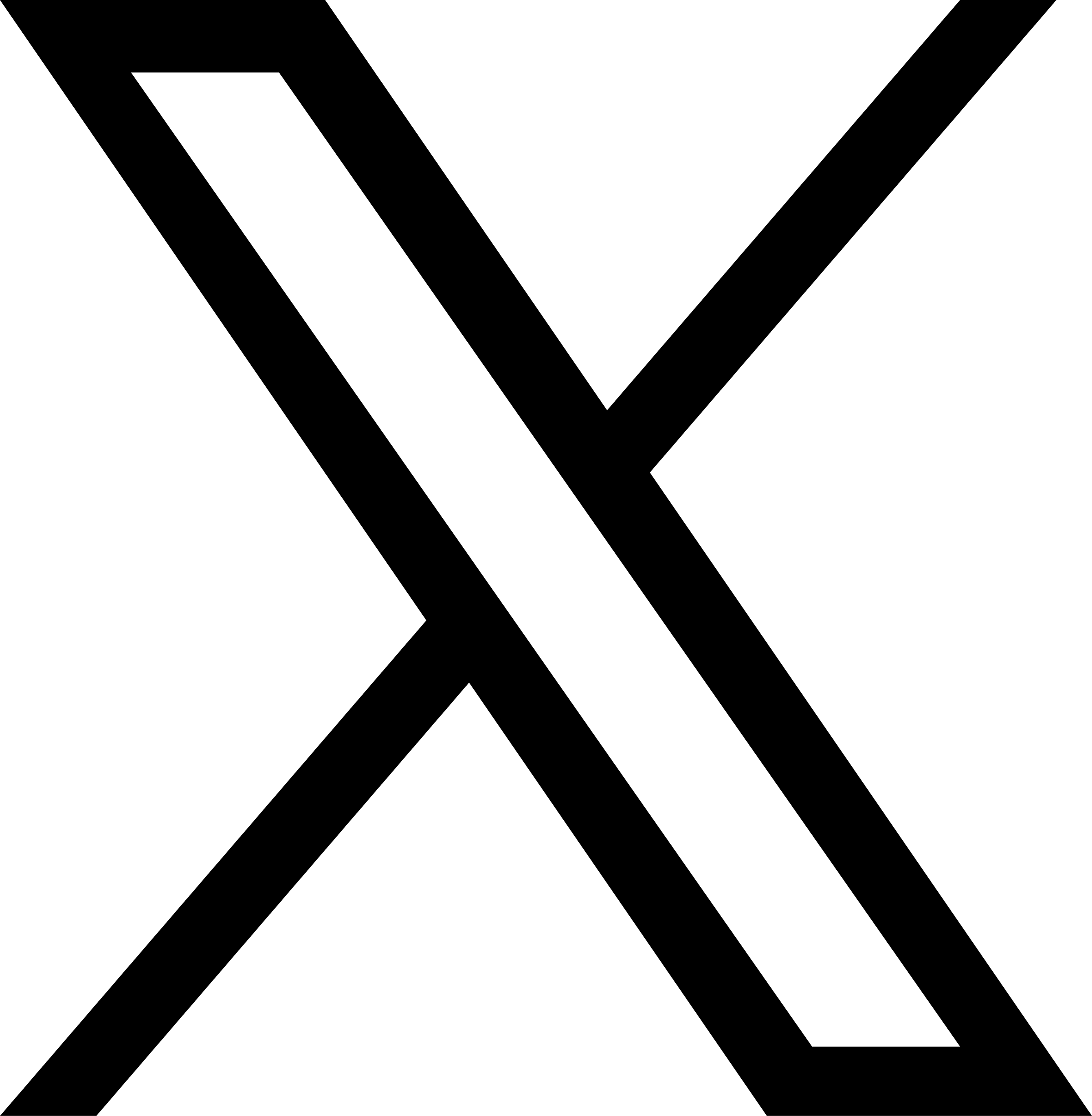
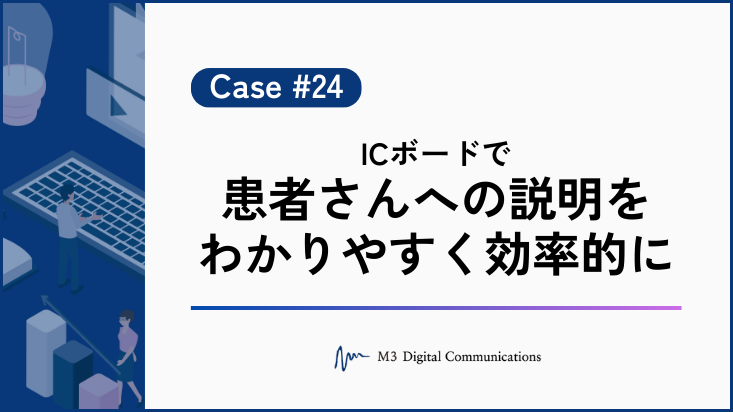
.png)
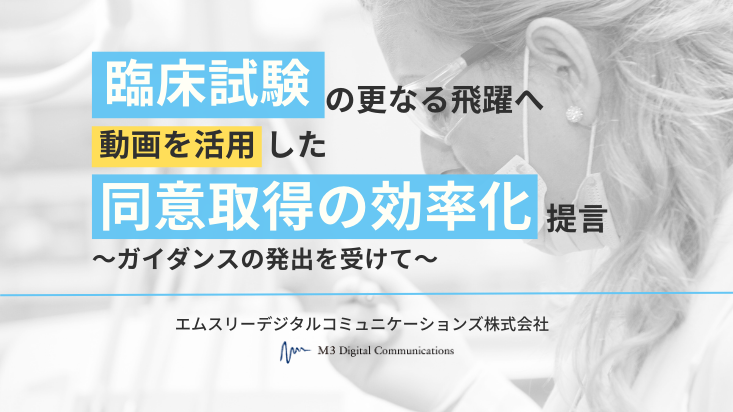
.png)